金融機関の実情を知る。有事になる前の対策を考える。
変化する時代を見据えた、これからの事業再生の流れとは
総会スタート! 事業承継、人口減少などの課題を共有する
2024年10月19日(土)、ミーティングスペース・AP東京八重洲にて、第19回目となるSRC総会・セミナーが開催されました。事業再生における課題が変化し続ける今、知識と情報をアップデートしながら学び合い、つながり合うために、全国12支部の志高い会員が集まりました。
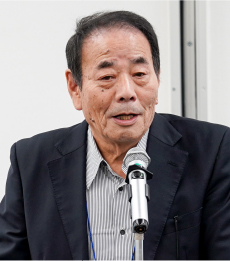
はじめにSRC代表理事の出津平氏より、開会の挨拶です。
「不良債権問題が世の中を席巻していた2002年、SRCは時代のニーズに基づき、事業再生の専門家集団として発足しました。同時にTMA(一般社団法人日本ターンアラウンド・マネジメント協会)を発足させ、事業再生士を育成してきました。20年以上経過し、時代はだいぶ変わりましたが、事業再生に対するニーズは減っていません」
そして現在は、新たな局面を迎えていると出津氏は語ります。
「今、中小企業の事業承継、後継者問題が大きくなっています。身内も継げない、M&Aもできない、その場合は『従業員の事業承継』が重要になってくるのではないか。我々事業再生の専門家によって、あっという間に業績回復した例もあります。SRC、あるいはTMAに、代替わりの時代の中で活躍をしていただきたいと思っております」
今後のニーズを示唆する出津氏の言葉に続き、議案の審議へと移ります。第1号議案「2024年度事業報告及び決算報告」、第2号議案「2025年度事業計画及び予算案」について、監事の木戸通夫氏が報告。出津平氏より第3号議案「理事改選」が説明され、3議案は全会一致で承認されました。

第1部の特別講演に先立ち、SRC理事及びTMA理事の立川昭吾氏が壇上へ。「今、地方の中小企業は本当に厳しい。なぜなら、人口減少が見えているからです」と、全国の支部から参加した会員へ課題を共有します。
「人口10万人以下の都市は、特に危険です。中小企業を育てなければ、日本の経済復興はない。その時代に合った経営者の育成も我々の課題です。統計数字、会計数字だけで考えないで、いろいろな面で変化を予測しながら事業再生というものを変えていく、それが私の願いです」立川氏の言葉で会場の空気がさらに引き締まり、いよいよ基調講演がスタートです。
寺岡雅顕氏が登壇! 金融機関を知り、事業再生のエコシステムを考える
専門家を招いての基調講演では、(株)エフティーエス代表取締役の寺岡雅顕氏が登壇します。寺岡氏は広島銀行融資部で企業再生支援業務を主導し、整理回収機構へ出向して企業再生支援を行った実績もあります。広島銀行復帰後はリスク統括部にて企業格付審査を担当後、融資企画部立ち上げに参加。株式会社エフティーエスを設立した後、現在は地銀、信用金庫、商工会議所等でセミナー・研修を行うなど幅広く活躍されています。
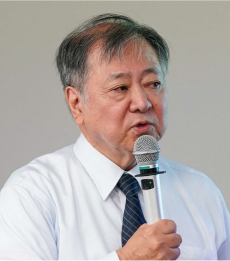
「皆さん、金融機関の言うことを正しいと思っていませんか? 彼らの言うことをお客さんがそのまま信じてしまうというのは、極めて恐ろしいことなんです」
強烈な印象を残す第一声に、会場全体が一気に引き込まれました。「金融機関の出身者が何を言っているんだと言われそうですが、あえて、金融界に対する過剰な期待を払拭しようというテーマでお話しさせていただきます」
講演のタイトルは、『金融機関の実情を踏まえ事業再生のエコシステムを考える ~金融機関に対する過剰な期待を払拭しよう~』。第1章として、「金融機関の実力を正しく理解する」というタイトルが提示されます。「そもそも金融機関には、融資人財を育てるシステムがありません」という寺岡氏。地銀でプロが育たない理由について、戦後の復興の中で大企業にとって直接金融の道が開かれたこと、プラザ合意を境に金融機関の渉外担当者の役割が変わったこと、金融検査における資産査定の廃止などが語られました。
第2章では、金融機関の支援で欠けている視点と、バランスシート・アプローチが解説されます。「本業支援、伴走支援という言葉が独り歩きしています。金融機関が本来やらなければいけない本業支援は、事業者が資金繰りに必要以上に心配することなく、経営に専念できる環境を整えること。最も重要なことは、バランスシートの安定です」と呼び掛けます。
第3章では、破綻が懸念された事業者を、上場を果たすまで再生させた事例を取り上げ、「コンサルは企業側の立場での発言をお願いする」など、寺岡氏の事業再生のスタンスが語られました。最後は、地域金融に空白地帯をつくらないエコシステムに言及。さらに「事業成長担保権」が「企業価値担保権」と名称を変えて新たな制度ができたことを「画期的」と評価する声が多いことに、「決してそんなことはない」と警鐘を鳴らし、中小企業にとっての課題を示して講演が締めくくられました。
ノンストップで約90分間、豊富な図解とともに貴重な情報を解説してくださった寺岡氏へ、会場から惜しみない拍手が送られます。常識を疑い、金融機関を過大評価することなく、現実を理解して進めるリアルな事業再生を学んだ時間となりました。
株式会社エフティーエス 代表取締役
寺岡 雅顕 氏
- 金融検定協会試験委員長(融資・事業性評価部門)
- 株式会社かがやき顧問

| 1978年 | 広島銀行入行。営業店勤務後、東京企画部で大蔵省・日銀・金融法人担当。 融資部では企業再生支援業務を主導。 |
|---|---|
| 2002年 | 整理回収機構出向。東京特別回収部で、拓銀債権を中心に弁護士とタッグで回収、 企業再生支援を行う。 |
| 2005年 | 広島銀行復帰。リスク統括部にて企業格付審査を担当後、融資企画部立ち上げに参加。 同行の目利き人材育成の研修体系の構築し、自ら指導を担当。 |
| 2013年 | 広島銀行を退社。 株式会社エフティーエスを設立。 地銀協、第二地銀協、全信協、全信組中央協会、金融財政事情研究会、銀行研修社、 近代セールス社、ビジネス教育出版社、地銀、信用金庫、商工会議所、士業団体等より、 研修を数多く受託。今日に至る。 |
・ベテラン融資マンの知恵袋(著)
・ベテラン融資マンの渉外術(編著楫野哲彦、樽谷祐一、寺岡雅顕)
・ベテラン融資マンの事業性評価(編著加藤基弘、樽谷祐一、寺岡雅顕)
・事業性評価力養成講座全3冊(編著加藤基弘、樽谷祐一、寺岡雅顕)
・新時代の中小企業経営支援の考え方(共著 樽谷祐一、藤井健太郎、寺岡雅顕)
・ポストコロナ金融本業支援実践講座テキスト1(共著 日下智晴、寺岡雅顕)
以上銀行研修社
有事になる前にできる対策は? 多様な視点からディスカッション
続いて、6名の会員が登壇。「『有事になる前の早期対応』がもたらす新しい事業再生の流れ」と題した、パネルディスカッションです。東京支部の井上真伯氏が進行を務め、ざっくばらんな雰囲気の中で意見交換していきます。


「今回のテーマは、有事に至る前の萌芽が見つけられるかということです。我々再生コンサルタントは、どうしても何か起こってから『お願いします』といわれることが多いのですが、実際にはその前に何かきっかけがあるのではないか。まずはそこからお話しいただきたいと思います」と井上氏が口火を切り、議論がスタートしました。

「ある民泊では、国際情勢がきっかけで経営が不振になりました。早めに売却を進め、M&Aが決まりかけていたのですが、金額で折り合いが付かずに破綻して悔しい思いをしました。成功例として、保険見直しなどで有事の前に気づき、M&Aが間に合った事案がありました」

四国支部の丸木章道氏は、税理士法人丸木会計士事務所の東京事務所所長を務めています。有事になる中小企業のリスクとして「担当者は、売り上げは把握できていても、原価がほとんど見えていない」という課題を挙げます。
「値上げより量を増やした方が良いなど、会社が傾いたときにどこに資源を振り分けるかを判断する材料を提供するのも、私たちの仕事ではないかと感じています」

日本サプライマネジメント協会監事である東京支部の藤田健氏が語ったのは、「内部統制の重要性」に加え、「人間を見る」というデューデリジェンスの視点です。
「自家用車で通勤できる、トイレに温水洗浄がついているなど、職場生活の隅々までケアされているか。設備の修繕が必要なのに、個人の力で維持している企業もあります。事業DDの結果を、財務DDなどときちんと統合できているかが大事なのではないか」

コスト経営研究所の中小企業診断士である東京支部の工藤工氏は、社会保険に言及します。
「社会保険事務所は、民間組織になって回収が厳しくなっています。金融機関の支払いがちゃんとしていても、社保を滞納していれば有事の始まりだと考えることができるのでは。今は基本的に2年しか猶予をもらえないケースが多い。社長もそれをわかっていないことがあるので、一緒になって話していくというのも専門家の仕事になってくると思います」

税理士事務所代表を務める大阪支部の永易秀一氏は、京都で独立開業されています。老舗の多い地域ですが、「時代の変化に十分に対応できていなかった会社は、どんどん淘汰されています」と実感を述べ、「伝統産業では機械化できない仕事が多いので非常に人手がかかるのですが、職人の数は減り、さらに高齢化しています。人手不足というより、職人不足という状況です」と、歴史ある地方ならではの課題を語ります。
全国的にも深刻になっている人手不足という問題については、事業会社だけではなく支援者側も厳しい状況に置かれています。それらの対策について、「SNSを活用する」「流動性が高い東京の考えを地方でも取り入れる」「有効なM&Aであれば積極的に」などのキーワードが飛び交い、議論が深まっていきました。
最後は、今後の姿勢についてひとことずついただきます。永易氏は「私の本業は税理士ですが、事業再生には今後も携わり、情報収集と人脈作りとしてSRCに関わっていきたい」、工藤氏は「社長だけでなく従業員との時間を取り、現場の人たちの不満をどう改善するかを考えたい」、丸木氏は「先進国でいるためには、中小企業を何とかしなければ。子どもたちに引き継ぐ使命だと思ってやり続けます」と力強くコメント。
藤田氏は「廃業ではなく、従業員も含めた『ハッピーリタイヤメント』を支援していくというサービスも真剣に考えたい」、萱嶋氏は「お客さまの強く美しいBSをという理念を大切に、貢献できる人間力と知識を伸ばしたいと思います」と語りました。
会場では参加者からの質問だけでなく、寺岡雅顕氏からのコメントも。議論をリードした井上氏が、最後に「金融機関がすべきこと、事業会社がすべきこと、我々がすべきことをきちんと分けて考えることが重要だと学びました。有事になる前にできることが多くあるというのが率直な感想です。ぜひ皆さんとともに頑張っていければと思います」と締めくくり、充実したディスカッションが終了しました。
会場を移しての懇親会では、ビュッフェ形式の食事を楽しみながらリラックスして語り合い、時には真剣に意見を交わしながら交流を深め、年に一度の総会・セミナーが幕を下ろしました。

